音の速さ:1気圧,t℃の空気中を伝わる音の速さV(m/s)は,
V=.+.t
うなり:が異なる2つの音の間で起こる.
1秒間あたりのうなりの回数をfとすると,
f=|f1 f2|
音1の振動数:f1
音2の振動数:f2
おんさAとおんさB(396Hz)を同時に鳴らすと,
うなりが毎秒5回聞こえた.おんさAの振動数はいくらか.
おんさAの振動数をfとすると,
5=|f 396|
f = ± + 396 = 4, 3 (Hz)
弦の振動
弦にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,
|
|
|
|
| λm = |
————————— |
|
(m = 1, 2, 3, ・・・) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弦の中の音の速さv
張力S(N),線密度ρ(kg/m)
|
 |
  |
|
| v = |
 |
|
|
 |
—————— |
|
|
 |
|
|
閉管
基本振動 3倍振動
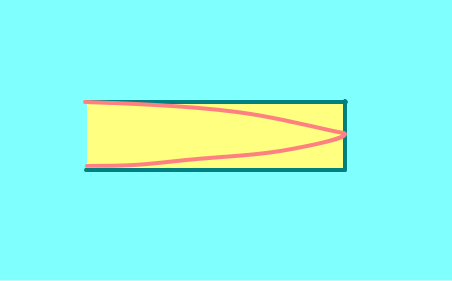
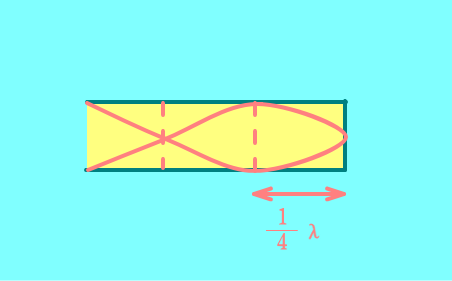
閉管の中にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,
|
|
|
|
| λm = |
————————— |
|
(m = 1, 3, 5, ・・・) |
|
|
|
|
|
|
|
|
開管
基本振動 2倍振動
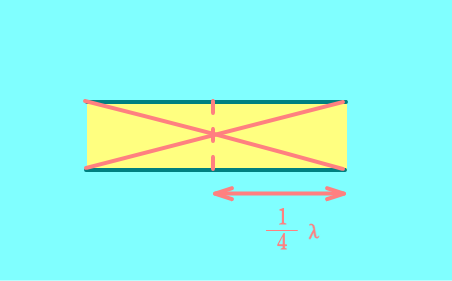
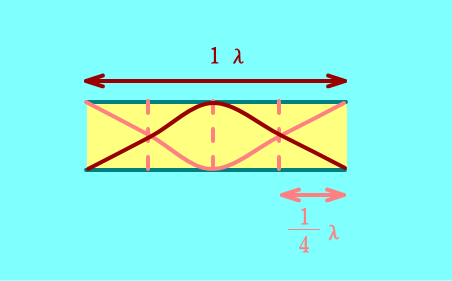
開管の中にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,
|
|
|
|
| λm = |
————————— |
|
(m = 1, 2, 3, ・・・) |
|
|
|
|
|
|
|
|
開口端補正:実際には,開口端よりも少し外側が腹になっている.
だいたいcmのことが多い.
閉管の問題で,共鳴する長さが,ℓ1と,もう少し長くしたときの
長さがℓ2で与えられているとき,ℓ1は,開口端補正も含んでいるので,
ℓ2 ℓ1をして,これを波長分の長さとして,計算する.
ℓ1は,波長と開口端補正を含んでいるので,半波長の分から
ℓ1を引くと開口端補正が求まる.
